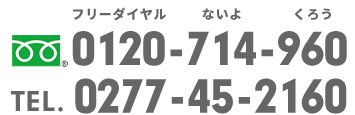-
2025.10.29
ブログ
相続手続きの全体スケジュール|2か月・3か月・4か月・10か月で進める実践チェックリスト

相続は、突然発生することが多く、「何から手をつけてよいのか分からない」というご相談をよくいただきます。
相続には法的な期限が定められており、後回しにすると申告漏れに発展するケースもあります。
この記事では期限を意識した相続の進め方をチェックリスト形式で整理しました。
目次
🧩【発生から2か月以内(目安)】まずは「遺言書・戸籍・財産」の確認
相続発生後、最初の2か月間は「基礎情報を正確に把握すること」が最重要です。
この段階での判断ミスは、後のトラブルや遺産分割の遅れに直結します。📝チェックリスト:2か月以内にできること(目安)
- 遺言書を探す(自宅・貸金庫・公証役場・法務局)
- 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言がある場合は、内容を確認
- 自筆遺言書を見つけたら、家庭裁判所で「検認」を申請(勝手に開封しない)
- 戸籍謄本を取得(出生から死亡までをすべて取得)
- 相続人の範囲を確定(配偶者・子・代襲相続人など)
- 財産・負債を一覧化(預金・不動産・保険・株式・借金など)
- 財産調査のため、金融機関・保険会社へ残高証明や契約状況を照会
📍POINT:
相続人・被相続人の本籍及び住民票の除票などは市区町村役場で取得できる場合がありますが、本籍地・転籍先によっては別の役場等の手続きも必要となります。
銀行や保険会社への照会は 一般に時間を要する場合がありますので、なるべく早めに手続きを開始することをおすすめします。
⚖️【3か月以内】相続放棄・限定承認の判断
相続財産を調べた結果、借金や保証債務がある場合は「相続放棄」または「限定承認」を検討します。
この判断は、相続の方向性を決める非常に重要なステップです。📝チェックリスト:3か月以内にやること
- 財産調査の結果をまとめ、資産・負債のバランスを確認
- 借入金や連帯保証、未払い税金の有無を確認
- 相続放棄をする場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 相続放棄:借金や債務が多い場合に有効。家庭裁判所で手続きが必要
- 限定承認を行う場合は、相続人全員の同意を得たうえで家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出
- 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ方法。相続人全員の同意と家庭裁判所手続が必要 放棄・限定承認どちらの場合も、申述時点で戸籍・住民票・相続関係説明図・財産・負債の状況などの資料を添付することが一般的です。
🕒 期限:相続開始を知った日から3か月以内
この期限を過ぎると、原則「単純承認」となり、すべての財産と負債を引き継ぐことになります。📍POINT:
相続放棄の判断は慎重に行いましょう。
一度放棄すると撤回は原則できません。迷う場合は、家庭裁判所または専門家(税理士・司法書士・弁護士)へ早めに相談をしましょう。参照:裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
参照:裁判所「相続の限定承認の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
💼【4か月以内】準確定申告の提出
被相続人が生前に収入を得ていた場合、その年分の所得税を申告する必要があります。
これを「準確定申告」と呼び、期限は相続開始を知った日から4か月以内です。📝チェックリスト:4か月以内にやること
- 被相続人の源泉徴収票・年金通知書・帳簿類を集める
- 所得の種類(給与・年金・事業・不動産など)を確認
- 医療費控除や社会保険料控除など、控除項目を整理
- 相続人全員で共同申告することを確認
- 税務署へ「準確定申告書」を提出し、納税または還付手続き
📍POINT:
税務署では、準確定申告の相談窓口があります。
提出が遅れると延滞税がかかるため、早めに資料を整理しましょう。
還付が発生する場合もあるため、税理士に依頼することで漏れのない申告が可能です。参照:国税庁「準確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
💰【10か月以内】相続税の申告と納付
財産の評価額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
不動産や株式など、評価が複雑な財産がある場合は、専門的なサポートが不可欠です。📝チェックリスト:10か月以内にやること
- 遺産分割協議書を作成(全相続人の署名押印)
- 財産評価(不動産は倍率もしくは路線価、上場株式は時価、預金は残高証明で確認)
- 相続税額を計算(基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例などを適用)
- 相続税申告書を作成し、税務署へ提出(提出期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
- 納付(申告期限までに納税を行う。)
📍POINT:
特例の適用については、税理士への相談がおすすめです。
✅【まとめ】期限を守ることが相続成功の第一歩
相続は感情的な部分と法的な部分が交錯し、冷静な判断が難しい局面も多いものです。
しかし、期限を意識して「やるべきこと」を一つずつ整理すれば、手続きは着実に進みます。🔑 相続スケジュール再確認
- 2か月以内:遺言書・戸籍・財産の確認
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
- 4か月以内:準確定申告の提出
- 10か月以内:相続税の申告と納付
相続を控えている方は、早い段階で専門家に相談し、
「期限」「証拠」「協議」の3点を確実に押さえていきましょう。
■申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。PROFILE

-
向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。
最新記事
- 2025年12月16日ブログ相続登記が未了でも相続税の申告は必要|先代名義不動産の基本ルールを実例で解説
- 2025年11月21日ブログ【知らないと損】火災保険の解約返戻金も相続税の対象?見落としがちなポイント
- 2025年10月29日ブログ相続手続きの全体スケジュール|2か月・3か月・4か月・10か月で進める実践チェックリスト
- 2025年9月30日ブログ複数の遺言があると相続税申告はどう変わる?実務の流れを解説
群馬県桐生市にある創業50年の実績がある税理士法人向田会計です。
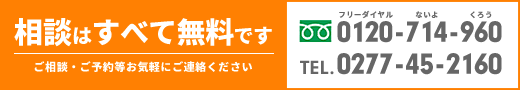
ブログ
相談は全て無料相続や相続税申告、事業承継のご相談はお気軽にどうぞ